 相談者
相談者大人って社会に縛られて不自由だよ。
家族や会社のために自分を犠牲にすることもあるし。
もっと自分らしく自由に生きていきたい。
 ゆめ
ゆめ今日はそんなあなたにおすすめの本を紹介するよ。
「エレファント・シンドローム」!
99%の大人が自由になれない理由と自由になる方法を説いた一冊だよ。
本当の自分になりたいあなたへの処方箋
子供の頃は自由で伸び伸びとやっていたのに、
大人になると社会やルールに縛られて、なんだか息苦しい。
別に今が死ぬほど嫌という訳ではないけど、
一度くらいすべての「責任」というものを投げ出して、
ハワイのビーチでコーラでも飲みながら、ぼーっと夕日が沈むのを眺めていたい。
そんな思いを大人なら、誰しも一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。
ある人は、世捨て人を見て言いました。
「羨ましい」
その言葉の裏に隠された思いとは、「私は不自由を感じている」なのかもしれません。
もしくは、成功を追い求めてやってきたけど、辿りついた場所は何だか虚しい。
- 幸せってどこにあるの?
- 自分らしさって何だっけ?と感じている方にもおすすめ。
それが、不自由さと自分らしさに悩む現在人への処方箋、浜口隆則氏著の「エレファント・シンドローム」です。
- 自由に生きていたい
- 自分の可能性を信じられる自分でいたい
- 将来フリーになったり、起業をしたい
- 本当の自由、本当の幸せを知りたい
- メンタルブロックを外したい
- インナーチャイルドを癒したい
- 一発屋の成功者ではなく、成功し続ける人になりたい
エレファント・シンドロームの概要

エレファント・シンドロームは、私たちの中にある「思い込み」について、深く掘り下げた一冊です。
これまで数々の経営人を支援し、自らも会社を経営する著者・浜口隆則氏は言います。
自分の中にある「思い込み」こそ、自由を妨げ、可能性を閉ざし、成功を遠ざけている、と。
そして、
その「思い込み」を手放すことがあなたを自由にし、可能性を広げ、成功へと導く、と。
自己啓発本にカテゴライズされる一冊だと思いますが、「目からウロコ!」ということだけでなく、正直、涙なしには読みきれませんでした。
というのも、本書が人に“与えるから与えられる“「ギブ・アンド・ギブン」の精神的に溢れているからです。
「ともに、本当の自分になって、自分の可能性を信じ、自由に生きていこうよ。その輪を広げようよ」
本文には書いていませんが、全編を通して、そう訴えかけてきているようです。
一般的な「HOW TOを教えてあげるよ」という本ではありません。
著者と読者が上下の関係にあるのではなく、著者が読者とともに歩んでくれるのです。
浜口氏は、過去のみっともない自分や勘違いしていた自分も、その失敗や過ちも惜しげもなく晒しながら、私たちと同じ目線に立って、ともに幸せと自由への道を辿ってくれます。
近年、読んだ自己啓発/ビジネス書の中では一番です。
評価は以下の通り。
| 文章の読みやすさ | 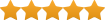 (5 / 5) (5 / 5) |
| 文章にこもった真心 | 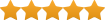 (5 / 5) (5 / 5) |
| 目からウロコ度 | 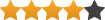 (4 / 5) (4 / 5) |
| ショートストーリー(比喩の面白さ) | 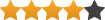 (4 / 5) (4 / 5) |
| 読むだけでブロック解除 | 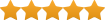 (5 / 5) (5 / 5) |
不自由なゾウが伝えていること〜思い込みこそが鎖だ!〜

筆者は、あなたの中の「思い込み」が、自由を妨げ、可能性を閉ざし、成功を遠ざけていると伝えています。
では、その「その思い込み」とはどういうことでしょうか。
プロローグで、本書の核心に迫るショートストーリーが書かれています。
それは、一頭の不自由なゾウの物語です。
【ストーリー】エレファント・シンドローム
ある場所に、大きなゾウがとても細い杭にロープでつながれていました。
大空を自由に飛び回っていた小さな鳥が、その大きなゾウの大きな頭に降り立ち、こう話しかけました。
「ゾウさん、こんにちは。いつも、ここにいますね」
大きなゾウは言いました。
「やぁ、トリくん、いつも気持ち良さそうだね。ボクは人を運ぶ仕事をしているんだ。子どもの頃から、人と一緒に生活をしているんだ。今はその人を待っているんだよ」
「ゾウさんは、どうして逃げないの?」
「逃げる? ボクだって、君のように自由に飛び回りたいよ。でも、ダメなんだ」
「どうして? ゾウさんは、そんなに大きいじゃないか。こんな細い杭とロープは簡単に引っこ抜けるよ。やってごらんよ」
「いや、ダメなんだ。昔、何度も試したんだ。でも、この杭とロープは壊せなかった。だから、無理なんだよ。やるだけムダさ。このロープはボクが壊せないくらい強いんだよ」
「大丈夫だよ。ゾウさんは、すごい力を持っているんだから、きっとできるよ」
大きなゾウは想像した。ロープを引きちぎって自由に走る姿を……。
それは心地の良い、爽快な妄想だった。
「ありがとう。何だか気持ちよかったよ。でも、今まで何度やってもダメだった。やっぱり無理だよ。……ボクは、学んだんだ」
引用:浜口隆則著「エレファント・シンドローム」
これは、実際ゾウを調教する時に行われる方法です。
調教された不自由なゾウは教えてくれています。
私たちを可能性を制限するのは、人でも環境でも社会でもなく、「できない」「いけない」「なれない」「それは悪いこと」「汚いこと」「やってはいけないこと」という思い込みなのだ、と。
賢い人や大きいゾウを支配するのは、ロープでも鎖でもなく、「思い込み」。
しかも、支配しているのは自分自身なのです。
これをメンタルブロックやインナーチャイルドとも言ったりします。
インナーチャイルドについては、私も記事を書いていますので、詳しくはそちらも参考ください。




そして本書では、多くの人が持ちやすい思い込みと、それらを捨ててきた著者の実体験が書かれています。
あなたの中にある8つの思い込み

エレファント・シンドロームでは、あなたの中にある思い込みを「8つ」にまとめ、各章ごとで掘り下げていきます。
その8つの思い込みがこちらです。
- 自分にはできない
- 失敗してはいけない
- 仕事は嫌なこと
- 運はコントロールできない
- お金は汚いもの
- 自分らしさは悪いこと
- 成功しないと幸せになれない
- 自分は一人で生きている
誰しもが一つや二つ、いやもっと当てはまるかもしれません。
本書では、それぞれの思い込みを、先ほど登場した調教されるゾウのような「ショートストーリー」ではじめにその実態を見せていきます。
そして、その後に著者の実体験を交え、詳しく紐解いていくスタイルを取っているのです。
「これはHOW TO本ではない」とは冒頭にお話しましたが、本書には「これをすれば思い込みは捨てられます」と言ったやり方や方法は書いていないのです。
 相談者
相談者それじゃあ、せっかく原因が分かっても解決できないんじゃない?
そう思うかもしれません。
けれど、これも冒頭お伝えした通り、著者が私たちと同じ目線に立って、ともに幸せと自由への道を辿ってくれることによって、自然と思い込みが溶けていきます。
そして、それがただ方法を教えられるよりも「効く」のです。
私も実際、読んだだけで「確かにこう言われると入ってくる!」と素直に受け入れることができ、ブロック解除までスムーズに進むことができました。
私が特に気に入ったのは「お金は汚いもの」という思い込みを外す「冷凍人間」のショートストーリーです。
昔、お金が大嫌いだった人が、人間の冷凍保存の被験者になり、未来に行きます。
その未来では、お金がなくなっていました。
代わりにコソカと呼ばれる社会貢献度を表す指数ができています。
社会に価値を提供するとコソカは増え、社会から価値を受け取るとコソカは減ります。
コソカをたくさん持っている人は、未来では尊敬される存在なのです。
なぜなら、たくさん貢献しながら、社会からの価値は受け取っていないのですから!
でも、これってまさに「お金」と同じ概念です。
けれど、社会貢献度を表す「コソカ」になると、それは汚いものだなんて思わない。
お金は汚いという思い込みは、お金の本質が理解できていないだけなのです。
読みやすいよう端折っていますが、こんなストーリーです。
いかがでしょうか。
たったこれだけでも、あなたの思い込みが少し変わっていきませんか?
私は確かに、「コソカをたくさん持っている人はきっと、心が美しい人なんだ!!」と思いました。
そんな風に、自分の中にある思い込みを捨てる旅を本書を通じてしていくことができるのです。
守・破・離〜思い込みを捨てることで自由になる〜

人は思い込みを捨てることで本当の自由、本当の自分らしさを手にしていくことができます。
そのことを著者は茶道の作法の成長段階を表す言葉「守・破・離」を使って説明しています。
「守」とは、文字通り守る時期。
師匠によって、基本や型というという教えを徹底的に刷り込まれていきます。
「破」で、教えをさらに洗練させ、自分でもあれこれ試していきます。
「離」で自分らしさや新しい方法論、オリジナリティを出していきます。
人間の成長もこれに似ています。
親に概念やルールを教えられる「守」時期。
基本を基軸に自分を模索する「破」の時期。
親から離れ、自分らしさに到達する「離」の時期。
成長段階で順当に、「破」「離」ということを行えればいいのですが、「守」だけで終わってしまうことが多いのだと、著者は語ります。
- 生きづらい!
- 不自由だ!
- 物事がうまくいかない!
そんな時は、「破」「離」の時期が来ているサインかもしれません。
成功し続ける秘訣

著者は「自分は一人で生きている」という思い込みを捨てる最終章で、成功し続ける人の秘訣を話しています。
これまでの思い込みに捨ててきたあと、最終的に辿り着くのがこのステージです。
この章が特に成功者としてだけでなく、自分の人生の舵取りをして、たくさんの人とともに幸せになっていく最大のポイントだと思いますので、掘り下げていきます。
秘訣1〜起きること100%自分の責任〜
成功し続けられる人は、「自分の人生で起きるすべてのことを100%自分の責任と考える」という特徴があります。
これを「自己効力感」と本書の中では語っています。
自己効力感は自己無力感の反対語であり、雪が降っても自分の責任だと考えるというのです。
 相談者
相談者雪が降っても自分の責任?
そんなの自分では天候なんか左右できないのに、そこまで責任を負う必要あるのかな?
私もはじめはそう感じたものの、読み進めていくと腑に落ちていきます。
自分が無力だと感じる人は、いいことも悪いことも人や環境のせいにしがちです。
だって、自分には現実を変える力なんてないのですから。
遅刻したら、「電車が遅れたから仕方ない」と自分を納得させていきますが、朝の電車が遅れやすければ一本早く乗ることだってできるのです。
けれど、自分は無力だと考える人は、自分の行動によって現実的を変えていけることを知りません。
だから、遅刻を繰り返し、「それは電車が遅れるから仕方がないのだ」と言い続けてしまうのです。
一方、自己効力感のある人は、「電車が遅れたから遅刻した」という事態も、自分には事態を変える力がある、と考えます。
朝、少し早起きして、一本早い電車に乗れば、例え電車が多少遅れたとしても遅刻はしないでしょう。
「自分の人生で起きるすべてのことを100%自分の責任と考える」人は、不可抗力に見える現実も変え続ける力を持っているのです。
秘訣2〜我を小さくし、人に感謝をする〜
そして、成功し続ける人に欠かせない能力のもう一つがとてもシンプル。
それが「感謝」です。
そのことを伝えるのに、本書では地獄と天国の様子を描いたショートストーリーが掲載されていました。
地獄と天国の景色はほとんど変わりません。
花がたくさん咲いていて、光に満ちあふれていて、ごちそうが並んでいます。
そして、ごちそうの周りには人々がいて、それを食べようとしています。
けれど、その箸が異様に長いのです。1.5mほどはありそうな箸を使って、
そのごちそうを食べようと試みます。
地獄ではそれを口に運べません。
かと言って、手で食べようとするのとその食べ物はたちまち消えてしまいます。
人々はお腹をすかせて苛立ち、あちらこちらで口論や取っ組み合いのケンカが起きます。
地獄の人々は目の前のごちそうをいつも、食べることができずにいるのです。
一方、天国の食卓では、その長い箸を使って、向かいの人の口にごちそうを運んであげます。
向かいの人も、長い箸で今後は同じように食事を口に入れてくれます。
天国の人はいつも相手を信頼し、そして、そのことに感謝し、お腹も心も満たされています。
天国と地獄のたった一つの違い。
それは「一人で生きている」か「みんなで生きている」か、その心の違いだったのです。
人ははじめからひとりでは生きていません。
成功者と呼ばれる人も多くの人のサポートがなければ、その高みに辿り着くことはできないのです。
成功し続ける上で欠かせないこの「感謝」とは、我さえよければ!という考えで突き進めば、やがて、人々のサポートを受けられなくなり、本人にそのしっぺ返しが来てしまうことを意味しています。
あなたの立場で一度置き換えてみてください。
もし、あなたが勤める会社の社長が偉そうにものを言い、自分だけの正しさを振りかざし、人を蹴落とし、自分だけ旨味を享受しようとしていたら、その人について行きたいと思うでしょうか。
一方、あなたを尊重し、目下のあなたにも敬語を使い、謙虚で、人の意見も積極的に取り入れようとしてくれる社長なら、あなたはついて行きたいと思いませんか?
「感謝」とは人望に繋がります。
人望がなければ、発展し続けることはないのです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
とにかく、自由、成功、発展と幸せへのヒントが散りばめられた一冊。
あなたに必要なものは、詰め込むことでも、学ぶことでもないかもしれません。
今、本書が伝える「8つの思い込み」を捨てることができたら、今まで突破できずにいた壁を易々と越えていけるかもしれません。
これからも、「光の心理学LABO」では、お悩みごとに最適な厳選の一冊をお届けしていきます。
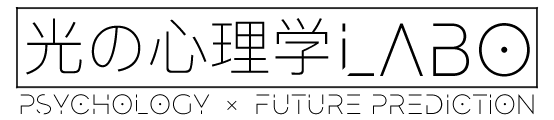



コメント