パターン4:虐待
体罰・性的な虐待も子供の自己肯定感を低くしてしまう大きな要因です。
守ってくれるはずの親から傷つけられる行為は、子供のその後の人生に大きな影を落としてしまいます。
「自分は傷つけられる存在だ」という価値観を構築してしまった子供は大人になっても、人に心を開きにくくなり、社会にも安心感を感じることが難しくなってしまいます。
自分のありのままの存在を肯定することができないばかりか、人・社会に対し、強い警戒心を持つようになってしまう傾向もあります。
パターン5:過度な期待
子供に期待を寄せることは親心としてあることですが、過度な期待は子供の負担になってしまうことがあります。
「こうあって欲しい」という思いは、もしかしたら親の思いとは別の子供のありのままの姿を否定することにもなってしまうからです。
子供は健気ですから、親の期待に応えようともしていきますし、その中で自分の本当の姿を否定し、自己肯定感を低くしてしまうことがあります。
パターン6:他者と比べる

「友達のあの子に比べて…」
「兄弟と比べて…」
そのような比較を常日頃行っている家庭では、子供は本来の自分の価値を見失ってしまいがちです。
常に競争の中に身をおくことになり、比べられた上でダメだと言われることで、子供は自分にもダメというレッテルを貼ってしまいます。
すると、大人になっても競争社会の中で他人と自分を比べて、卑下することが多くなってしまいます。
パターン7:条件つきの愛情

「これができたら愛をあげる」
そんな条件付きの愛情は、子供のそのままの価値ではなく、できたことの価値を認めるような行為になってしまいます。
すると子供は「できない自分には価値がない」と感じるようになり、成果ばかりを求めるようになってしまいます。
無理に「いい子」でいようとする子供も多いでしょう。
失敗も間違いも含めて、あなたには価値があることを教わる家庭と、成果があって認められる家庭では、子供の自己肯定感も大きく変わってしまいます。
パターン8:両親の不和

子育ての面だけでなく、両親の不和も子供に大きな影響を与えるようになってしまいます。
幼い子供は自分の気持ちを上手に話すことができませんが、大人が思うよりずっと大人たちの状況を察しています。
子供の主食は両親の笑顔です。
両親の仲が悪く、家庭でケンカが絶えないなどの環境だと、子供は必要以上に気を使ったり、緊張してしまいます。
自分が我慢することで家庭をよくしようとする子供心は、自分のありのままの姿・気持ちを無意識に抑えこむことに繋がってしまい、子供の自己肯定感を低くしてしまうのです。
パターン9:両親が幸せではない
先ほど「両親の不和」でもお伝えしたように、子供の主食は両親の笑顔です。
子供は無条件で両親の幸せを願い、愛を与えようとする存在。
けれど、経済的・家庭的、または人間関係や仕事などの様々な要因で親が幸せそうではない家庭の場合、子供は親に過度に気を使うようになっていってしまいます。
自分の素直な感情を押し込めたり、無理にいい子・できる子になろうとするケースもあります。
また、特に幼少期の子供は親と精神的に一体化しやすいため、両親が不幸だと子供の自分ごとのように不幸と感じるようになります。
そのような状況が日常的にあると、子供の自己肯定感もどうしても低くなってしまうのです。
パターン10:家庭の経済的不安

両親の不和と同じく、家庭の経済的な不安も子供に不安な影響を与えてしまうことがあります。
ただ、これは経済的な不安を抱えていても両親が明るく前向きに暮らしている場合は別です。
経済的な不安から家庭でも子供に日頃から我慢を強いる状況であったり、家庭でも両親が困窮している様子などがあった場合、子供は敏感にその状況を感じ取り、精神不安を抱えるようになってしまいます。
「わがままを言わないように」「いい子にしよう」「我慢しよう」などの子供が自分の素直な気持ちを押さえ込んでしまうパターンの場合は、自己肯定感も低くなる傾向があります。
自己肯定感が低いことで生まれる問題
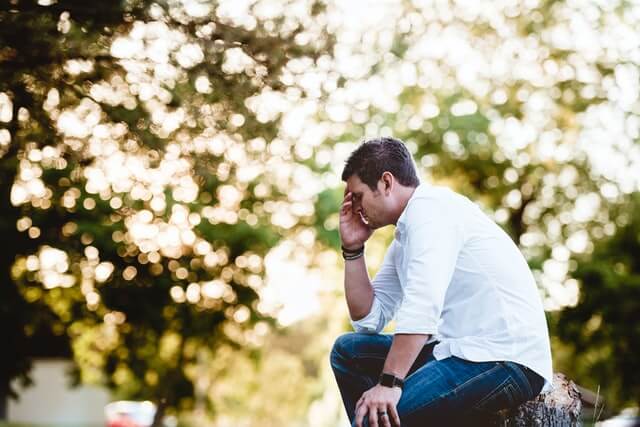
自己肯定感が低いまま大人になっていくと、生活の中であらゆる問題を抱えやすくなってしまいます。
中でも人間関係は、最も大きな問題と言えるでしょう。
アドラー心理学では、「すべての悩みは対人関係の悩みである」とまで断言しています。
まず、自己肯定感が低い人は「ありのままの自分」を自分で認めることができません。
それは親から「ありのままの自分」を認められた経験がなかったため…。
すると、どういったことが起きていくのかというと、自分に欠けている承認を外側から満たそうという行動をとっていくのです。
つまり、行動原理が人から「認められよう」「許されよう」になっていってしまいます。
承認欲求とは、自己承認ができないために他者からの承認を得ようとしすぎていることが原因にあるのです。
人から「認められよう」「許されよう」が行動原理になった場合、人に必要以上に気を使ってしまったり、顔色をうかがったり、嫌われるのを恐れて断ることができなかったり、または認められるために自分の心を無視してまで頑張ってしまうこともあります。
けれどそういった人は「いい子」「いい人」と周りから言われやすいので、認められるために努力をする自分が評価されていると思い、なかなかその苦しい行動を止めることができません。
すると、次第に人の中で疲弊し、それが大きくなることで生きづらさにまで発展をしていってしまいます。
また、自己肯定感が低いと恋愛もつまづきやすくなってしまいます。
自分が愛される人から「認められない」「愛されない」という価値観があるため、愛を求めて恋人に依存的になったり、逆に愛されようと健気に頑張りすぎてしまったりするのです。
人間関係のつまずきの根幹には、自己肯定感があります。
そこで自分の行動原理を見直し、自己肯定感を高めていくことが大切になってくるのです。
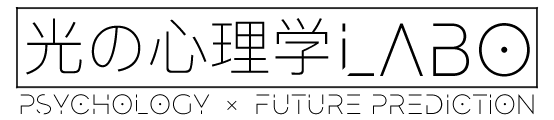

コメント